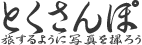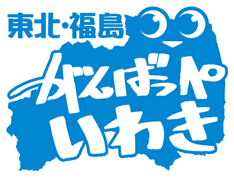今日の『がんばっぺいわき!スナップショット』は、かもめの視線の空撮家・酒井英治さんの撮影現場にいらしていた大学生の皆さんです。 GWを利用してボランティアを含め、調査にこられたそうです。

空撮家の酒井さんと旅館みさきのご主人、そして、武蔵野美術大学の皆さんです。
現在、大学の3年生で、環境デザインという選択科目を選履修しており、ソーシャルデザイン(デザインで社会の問題の根本解決を目指す)をテーマに活動中とのことでした。
今年は前年度の活動を引き継ぎ、被災地のソーシャルデザインという枠で、全4グループ(総勢20名)が活動中で、女川や気仙沼などで活動しているグループもあるとのこと。

自分たちが被災地の何に、誰に、何を貢献したいかを決め、まずは現状を把握した後、本当に求められているものを見極め、最終的には現地の人と提携しながら、なにかデザインを地域の利益に還元することを目的にしたいと話されていました。
ボランティアに参加するだけじゃない。被災地を考え、その後の街づくりなど、学びにつなげたいという思いを感じました。

今回は、東北コットンプロジェクトから、いわきコットンプロジェクトを知り、参加してきたとのことでした。
いわきコットンプロジェクトは、有機肥料などによる土壌作りを行い、農薬の類を一切使わずに栽培するオーガニックコットンの栽培を支援する活動です。遠野地区為朝集落で行われています。
この地区は、山あいにある十三世帯・四十二人が暮らしている小さな集落で、湧き水を引いた簡易水道で水を供給していました。3年ほど前から、ゆずと梅を使ったジャムの販売や、野菜の収穫体験・ドレッシング作りなどで地域おこしをしていましたが、昨年の4月11日に起きた震度6弱の余震により、簡易水道の利用は止まり、今も日々、タンクを積んで水汲みに通っています。
そこで、地域おこしの世話人をしている折笠茂子さんはそんな現状を機会あるごとに外に伝え、寄付金を集めたり、ボランティアを募る活動を続け、今回のプロジェクトにも積極的に取り組み、集落を盛り上げています。
その活動は様々なメディアに取り上げられています。
ちなみに、被災地域での耕作物生産に関して、諸々の意見・考えがあるかと思いますが、生産地の明示や放射線量の測定など、消費者が製品を選択する権利が確保できる製品化・流通であることは常識的なことです。この活動については、始まったばかりでもありますし、被災地の復興を模索する活動として、温かいご支援を頂ければと思います。

大学の授業履修をきっかけとして、被災地の支援活動について行動を起こしていただける方もいます。いろんな方が、被災地の、日本の復興につながる活動をしてくださってると感じました。